新築住宅や中古住宅購入時には、様々な補助金を受け取れる可能性があります。
補助金の対象となる要件はそれぞれ異なりますが、知っているだけで数万円〜数十万円を貰える可能性があります。
補助金の種類

新築住宅を購入する際には、要件を満たすことで受け取れる可能性がある補助金が複数存在します。計画的に利用することで、「夢のマイホーム」購入がグッと近づきます‼︎
今回はそれぞれの補助金を詳しく紹介していきます。
新築物件は、中古物件と比べると購入金額は高騰しますが、補助金によるサポートなどを受けることができると、その負担を大きく減らすこともできます。
すまい給付金
すまい給付金とは、増税を境に始められた制度で、新築物件購入を行った際に現金がもらえる制度です。もらえる金額は年収などの条件によって決まり、最高で50万円となっている。
(宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が給付金の対象です。)
消費税率の引き上げにより不動産価格が高騰し、負担が大きくなることで新築物件購入に後ろ向きになる人が多くなりました。
国は、この負担を減らしてマイホームを購入しやすくするための制度を作りました。それが『すまい給付金』です。対象となるのは、収入額の目安が775万円以下の方。
この制度は、新築住宅・中古住宅とも利用できますが、対象となる新築住宅は、これまでに人の居住の用に供したことのない住宅、かつ工事完了から1年以内のものと定められています。
要件は「住宅ローン利用」と「現金購入」で違ってきます。
住宅ローン利用時の要件
- 床面積が50m2以上の住宅
- 施工中に検査を受け、
1:住宅瑕疵担保責任保険に加入
2:建設住宅性能表示の利用
3:住宅瑕疵担保責任保険法人から保険と同等の検査を実施
この3つの条件のうち1つ以上をクリアしなければならない。
現金購入時の要件
- 住宅取得者の年齢が50歳以上
※引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢 - 収入額が650万円未満
- フラット35Sと同等の基準を満たす住宅
年収別の給付金額は以下の通りです。
| 450万円以下 | 50万円 |
| 450万円超~525万円以下 | 40万円 |
| 525万円超~600万円以下 | 30万円 |
| 600万円超~675万円以下 | 20万円 |
| 675万円超~775万円以下 | 10万円 |
最大の給付金額は50万円であるが、その金額は「給付基礎額」×「持分割合」で決定されます。
給付基礎額は都道府県民税の所得割額によって決定され、持分割合は不動産の登記事項証明書に記載されている割合となっています。
なお、中古住宅(買取再販中古住宅)の場合は、対象要件として耐震性能(現行の耐震基準)を満たす要件が必要となります。反面、フラット35Sと同等の基準を満たす要件は必要なくなります。
ZEH補助金
ZEH住宅とは、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)省エネ基準比20%以上を実現し、さらに再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー収支をゼロにすることを目指す住宅です。
ZEH住宅の補助金は、ZEHの性能により3つに分けられ、【ZEH】【ZEH+】【次世代ZEH+】に分類されます。
【ZEH+】はより省エネに特化し、電気自動車充電設備などを設置し、再生可能エネルギー使用、消費を促す住宅のことをいいます。
【次世代ZEH+】はZEH+の機能に追加して、さらに蓄電システム、燃料電池などの再生可能エネルギーの自家消費拡大につながる設備を導入した住宅のことをいいます。
このZEH住宅は、ZEHビルダーやプランナーとして登録されている施工会社などによる住宅建築で補助金を受け取ることができます。
ZEH補助金の要件
- ZEHロードマップにおける「ZEHの定義」を満たしていること
- 登録されたZEHビルダー/プランナーが設計、建築、改修又は販売を行う住宅
この補助金は、一律60万円を受け取ることができ、ZEHに加えて再生可能エネルギーの自家消費を拡大したZEH+として認定されれば、「ZEH+実証事業」という名目で一律105万円が補助されます。
このZEH支援事業は、一般社団法人の公募による抽選を行い支給されます。そのため、必ずしも補助金を受け取れることができるわけではないことへの注意が必要です。
日本政府の方針としては、2030年には新築されるほぼすべての新築住宅をZEHにすることを目標としています。
今後はZEH住宅が増えてくることが考えられ、この補助金はいいつまで続くかはわからない現状です。
地域型住宅グリーン化事業補助金
この事業は、長期優良住宅や低炭素住宅などの省エネルギー性能に特化した木造住宅を新築する場合際に、建築業者に給付される補助金です。
国土交通省に採択された、同一地域の中小住宅生産者や木材、建材の流通を担う会社などのグループが設定、建築を行う住宅に対して支払われる補助金で、申請や受取は担当した施工会社が行います。
新築住宅の場合、いくつかの種類に分けられます。いずれも木造であることが申請の前提条件となっています。
長寿命型
中小住宅生産者によって建築され、定められた講習を受けた人物が設計や施工を担当する住宅がこの『長寿命型』にあたります。
補助金は対象額の経費のうち1割以内かつ110万円までと定められており、構造材の50%以上が地域材(地元産の木材)の場合は追加で20万円、三世代同居対応住宅の場合は追加で30万円が補助金支給されます。
高度省エネ型
行政庁より低炭素住宅としての認定や性能向上計画の認定を受けた住宅がこの『高度省エネ型』にあたります。
補助金の金額は長寿命型と同様で、経費の1割以内かつ110万円までとなっており、構造材の50%以上が地域材なら追加で20万円が、三世代同居対応住宅の場合は追加で30万円が補助金支給されます。
また、一定の要件を満たすことで、ゼロ・エネルギー住宅として認められた場合は、経費の1/2以内かつ140万円までを上限に補助金が発生します。
この場合にも、50%以上が地域材でつくられていると20万円、三世代同居対応住宅なら30万円が上限に追加されます。
省エネ改修型
消費性能基準等を定める省令に相当する建築物エネルギー性能を持つ住宅がこの『省エネ改修型』にあたります。
補助金額は住宅1戸あたり一律50万円とされており、条件により増減することはありません。
次世代住宅ポイント制度
この制度は、現金でなくポイントで支給される部分が最大の特徴で、最大35万ポイント受け取ることができます。
次世代住宅ポイント制度の要件
- 新築物件が認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅・ZEH(ゼッチ)のいずれかに該当する場合
- 断熱等性能等級4以上などの性能を有する住宅を新築した場合
- 耐震性を有していない住宅の建て替えやリフォームを行った場合
- 家事負担軽減に資する設備を設置した住宅を購入した場合
家庭用燃料電池システム導入支援事業補助金
家庭用燃料電池「エネファーム」とは、水素と酸素から電気と熱をつくるシステムであり、エネファームを住宅等に導入する場合に、その購入代金の一部が国から補助されるという制度です。
この補助金の金額は定額補助金と追加補助額に分かれており、定額補助金では補助対象エネファームの機器代+工事費が基準価格以下の場合は8万円、基準価格を上回り据切価格以下の場合は4万円に定められています。
個体酸化物形燃料電池の場合には、基準価格は123万円、裾切価格は134万円に設定されています。
追加補助額も存在し、既築住宅に新しく設置する場合には、LPガス、寒冷地仕様のそれぞれの場合において3万円が支払われます。
自治体の補助金制度
意外と見逃してしまうことの多い『市町村別の補助金』ですが、特に過疎地域では多くの補助を行ってもらうことができる場合もあり、各市町村のホームページなどを調べる必要があります。
その種類は様々で、新築にかかる建築費用やリフォーム代金の補助や引越し費用の給付、バリアフリー化にかかる工事費に対する補助など多岐に渡ります。
この『自治体別の補助金』は、その自治体の地域の会社の利用や、当該地域に住宅を構えて住民票を移すことなどの条件をクリアすること支給が認められることが一般的です。
そのため田舎の方が多くの補助を受け取ることができる場合があります。
まとめ

これらの補助金の種類は多岐に渡り、それぞれの補助金を理解し、利用することは難しい場合もあります。
しかし、うまく活用することで「夢のマイホーム」購入への一歩になることは間違いありません。
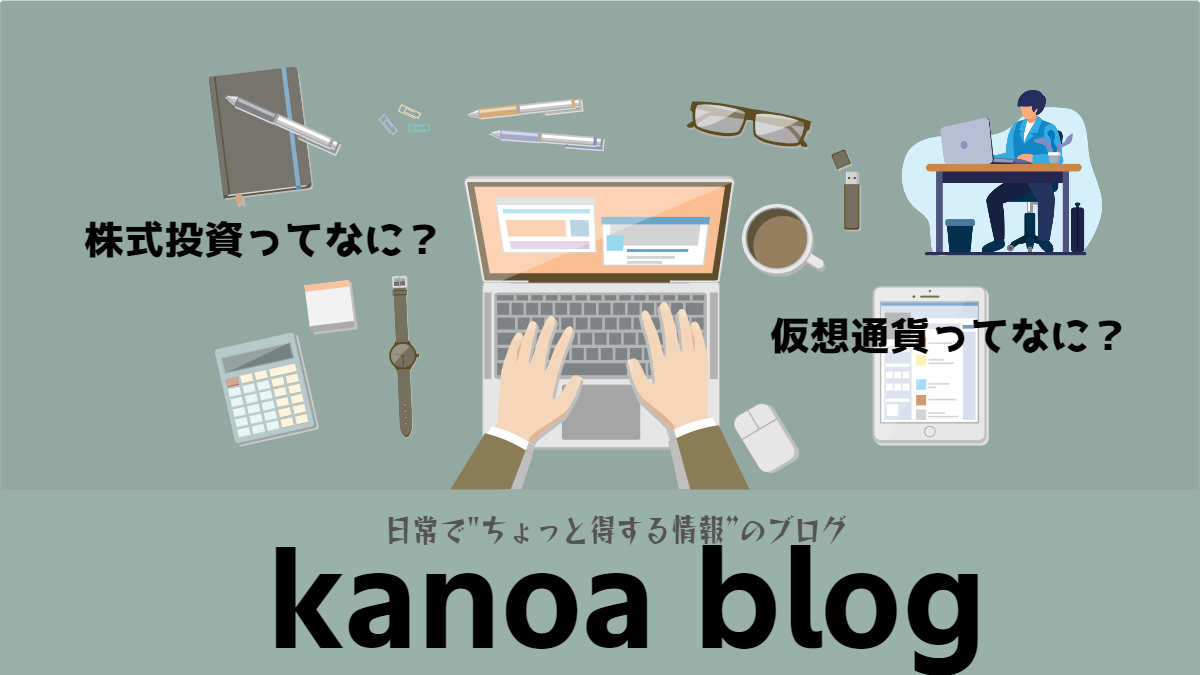
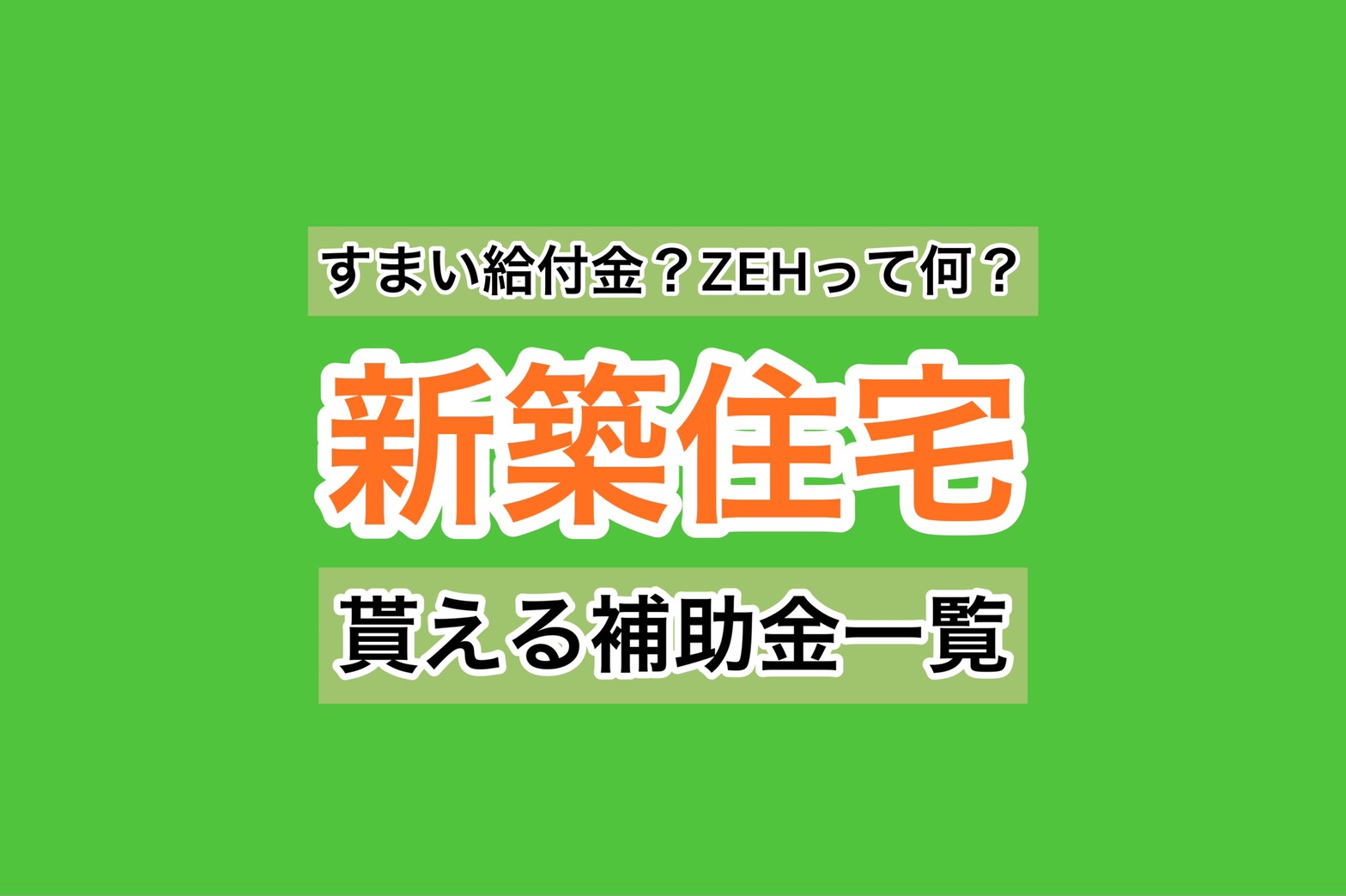

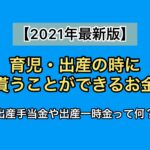
コメント