役所では教えてくれない
『貰えるお金』『返ってくるお金』の紹介です。

1.すまい給付金
概要
「すまい給付金」は消費税率引上げによる住宅取得者の負担を減らすために現金を支給したりする制度のことです。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
しかし、すまい給付金制度は、住宅ローン減税の効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

対象者
- 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
- 収入が一定以下
- 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
- 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
- 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下、[10%時]収入額の目安が775万円以下
- (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
対象の住宅
- 引上げ後の消費税率が適用されること
- 床面積が50m2以上であること
- 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

また、私の住む佐賀県で言うと『多久市』や『大町町』などでも独自の制度があります。
2.自動車購入の際の補助金
概要
電気自動車の「国の」補助金は3つあり、それぞれに対象、条件に合わせて、3つのうちどれか1つを選んで受給可能です。
環境省補助金
補助金 最大80万円
対象 個人や民間事業者
条件 クリーンエネルギー自動車の購入に加えて
- 自宅/事務所等の電力を再生可能エネルギー100%電力を調達すること
- 政府が実施する調査にモニターとして参画すること
(4年度に渡り毎年1回程度のアンケート調査に協力)
経済産業省補助金
補助金 最大60万円
対象 個人のみ
条件 クリーンエネルギー自動車の購入に加え
- 充放電器(V2H)/ 外部給電器(V2L)導入とあわせての車両購入であること
- 車両や設備の活用状況等のモニタリング調査に参画すること
- 災害が起こった場合、可能な範囲で自治体に協力すること
CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)
補助金 最大42万円
対象 個人、地方公共団体、その他の法
条件 クリーンエネルギー自動車の購入のみ

3.就学援助制度
概要
これは学校教育法第19条において,「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」と定められており、市町村により最大で4万円の援助を受けることができます。
茨城県日立市や大阪府摂津市は、収入などの条件なしにランドセルを現物支給してくれる自治体でもあります。
対象者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
補助対象
4.高額医療制度
概要
私たちが病気やケガで医療機関にかかるとき、自己負担額は原則3割ですが、高額な医療費がかかった時に、上限を設けて負担を抑えてくれる制度が高額療養費制度です。

自己負担上限額
【70歳未満の区分】
|
所得区分 |
自己負担上限額 |
多数該当 |
| 標準報酬月額 83万以上 報酬月額 81万以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 標準報酬月額 53万〜79万以上 報酬月額 51.5万〜81万以上 |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% |
93,000円 |
| 標準報酬月額 28万〜50万以上 報酬月額 27万〜51.5万以上 |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 標準報酬月額 26万円以下 報酬月額 27万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
| 低所得者 被保険者が市町村民税の非課税者等 |
35,400円 |
24,600円 |
※世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合など、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
5.教育訓練給付金
概要
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。

対象者
- 雇用保険の支給要件期間が3年以上
- 受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
- 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
支給金額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
6.被災ローン減免制度
概要
自然災害の影響で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りの方を対象として、一定の要件を満たす場合に、住宅ローン、事業性ローンなどの債務の免除・減額を申し出ることができる制度です。
金融機関の承諾が条件となり、自身の貯蓄の最大500万円と公的な支援金などを手元に残したうえで、可能な範囲で返済を行います。それでも全額返済が不可能な場合は免除してもらえるのです。
自己破産とは違い、これ以降も新たなローンが組める可能性が高い、という利点もありますが法的拘束力はなく、全国銀行協会が中心となった制度です。

対象者
- 住居、勤務先などの生活基盤や事業所、事業設備、取引先などの事業基盤が災害の影響を受けたことによって、住宅ローンなどの借入れの返済ができない方、または、近い将来、返済が困難となることが確実と見込まれる方
- 災害前は、住宅ローンなどの借入れについてきちんと返済していた方 など
メリット
- 信用情報機関の登録などの不利益を回避ができる
- 弁護士など「登録専門家」の費用が不要
- 手元に預金は500万円まで残すことができる
7.その他の補助金等
出産・妊娠・子育て
1.出産手当:1日の支給額=支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
2.出産育児一時金:妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円))
3.特定不妊治療助成金:地方自治体により異なる 例)東京都の場合
| 所得制限 | 制限なし |
| 助成額(特定不妊) | 1回30万円(治療ステージC・Fは10万円) |
| 助成額(男性不妊) | 1回30万円 |
| 助成上限回数 | 1子ごとに6回まで(40歳以上43歳未満は3回まで) |
4.児童扶養手当:母子家庭や父子家庭となった家庭に対して、最大月額4万2200支給されます。
※実家等に戻ることで対象外となる可能性があります。
5.子供用メガネ保険適用:小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズについて、メガネの場合は38,902円まで。


6.私立幼稚園奨励費補助金:子ども・子育て支援新制度未移行の私立幼稚園、 特別支援学校幼稚部、国立大学附属幼稚園の園児に対して、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4が負担を行い、最大月額25,700円の給付を受けることができる。
介護・福祉
1.介護休業給付:負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業の場合、介護休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、介護休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。
- 平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度
- 平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13,4万円程度
- 平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円程度
2.訪問介護医療費控除:「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。
冠婚葬祭
1.葬祭費給付金:葬祭費補助金制度とは、国民健康保険や社会保険・共済組合に加入している方が亡くなった際に葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金制度で最大7万円を支給されます。
国民保険の場合
葬祭費給付金制度とは、被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、費用が支給される制度のことです。国民健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に保険証の返却・変更の手続きを行います。
| 国民健康保険加入の方 | 50,000~70,000円 |
|---|---|
| 後期高齢者保険加入の方 | 30,000~70,000円 |
| 申請期間 | 2年間 |
| 申請・問い合わせ先 | 市・区役所の保健年金課 |
健康保険の場合
埋葬料給付金制度とは、被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。
| 埋葬料 | 上限50,000円までで実費精算 |
|---|---|
| 申請期間 | 2年間 |
| 申請・問い合わせ先 | 全国健康保険協会 |
国家公務員の場合
| 葬祭費 | 100,000~270,000円各組合により異なります |
|---|---|
| 申請・問い合わせ先 | 加入している各共済組合 |
埋葬費
埋葬費給付金制度とは、被保険者本人が死亡した場合で、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される埋葬にかかった費用をいいます。故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
| 埋葬費 | 50,000円 |
|---|---|
| 申請期間 | 2年間 |
| 申請・問い合わせ先 | 全国健康保険協会 |
その他も多くの給付金や補助金がございます。
各地方自治体に問い合わせることで確認することができます。
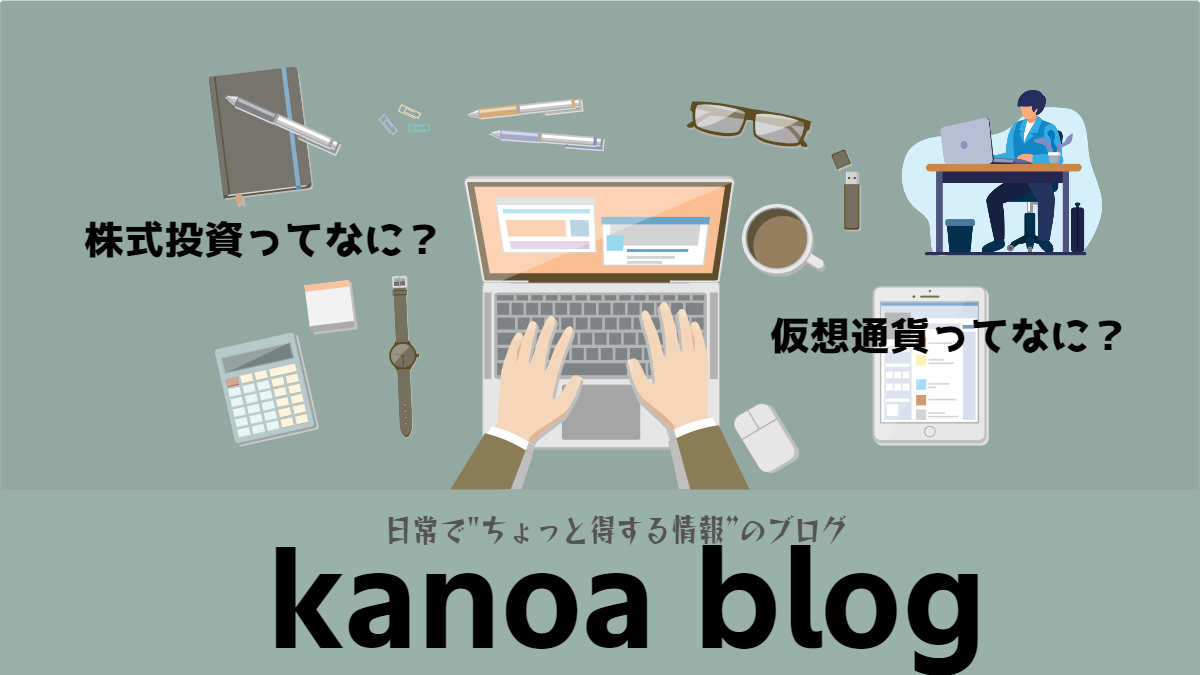
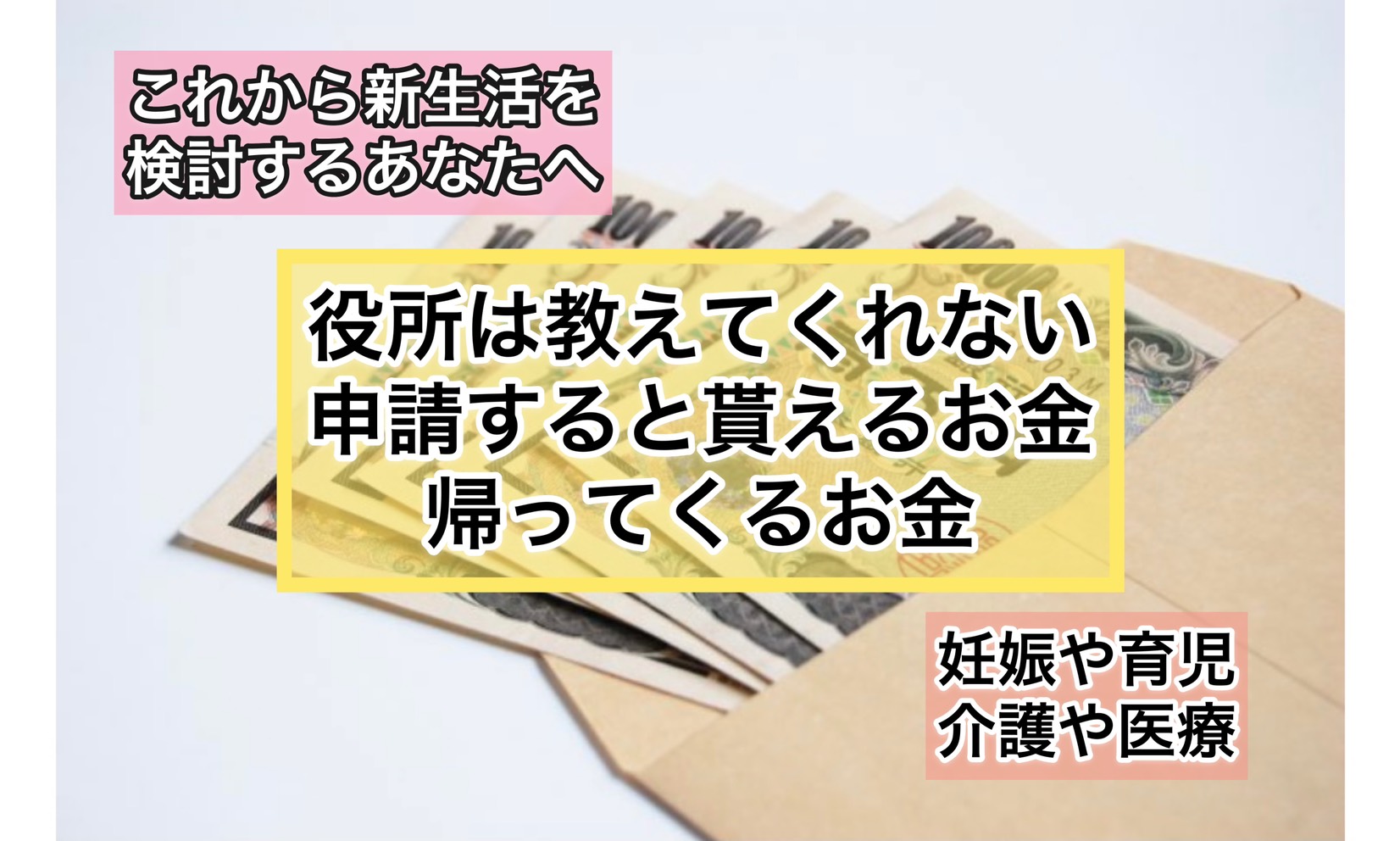
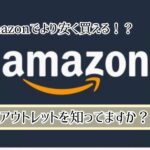

コメント